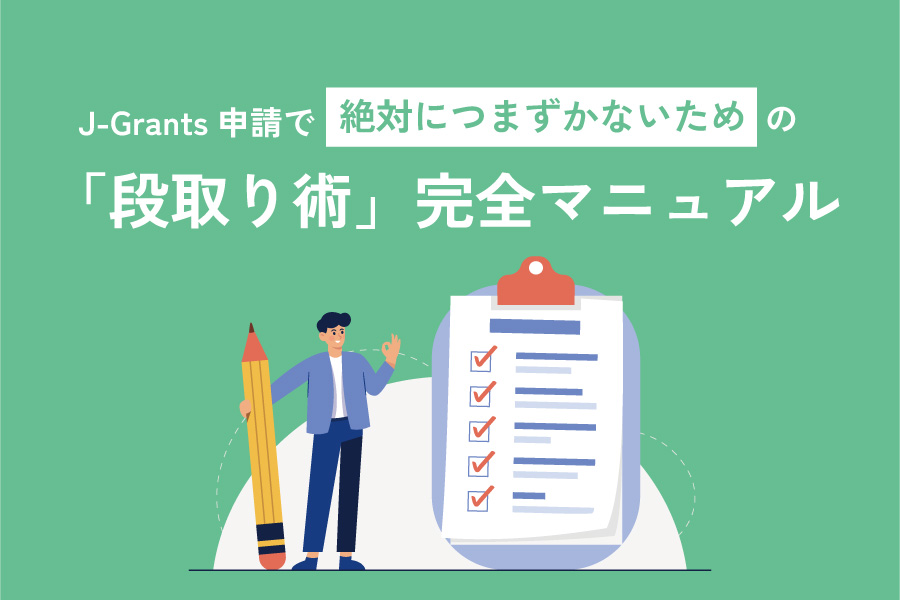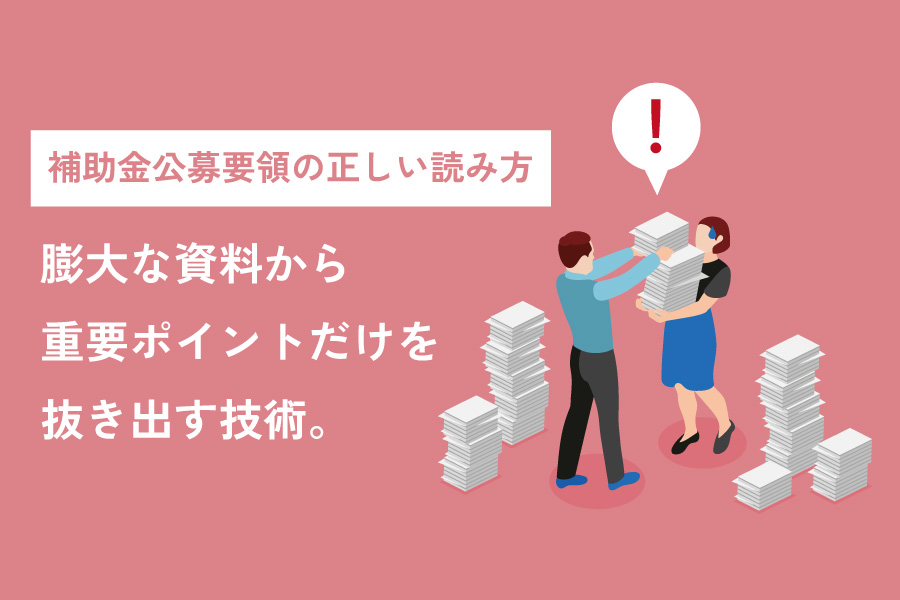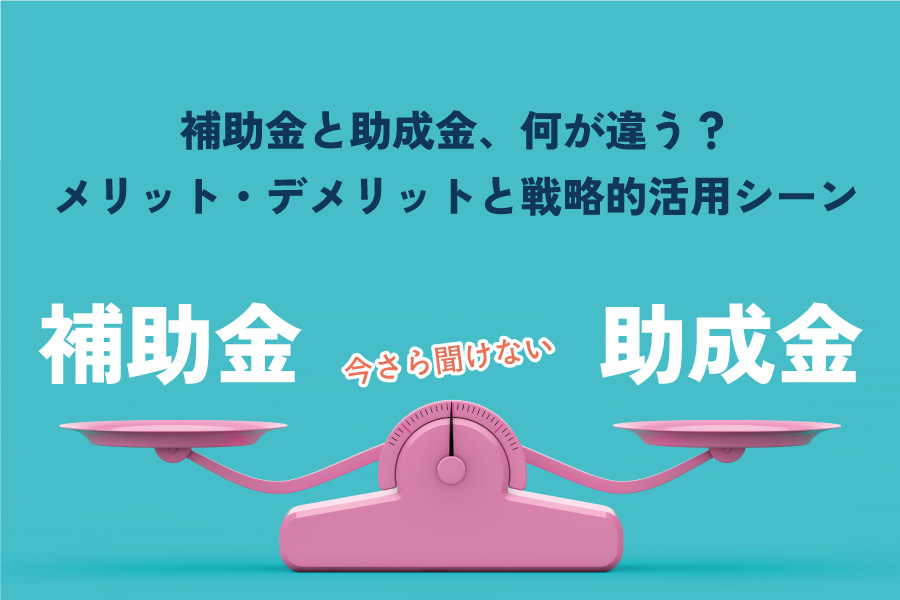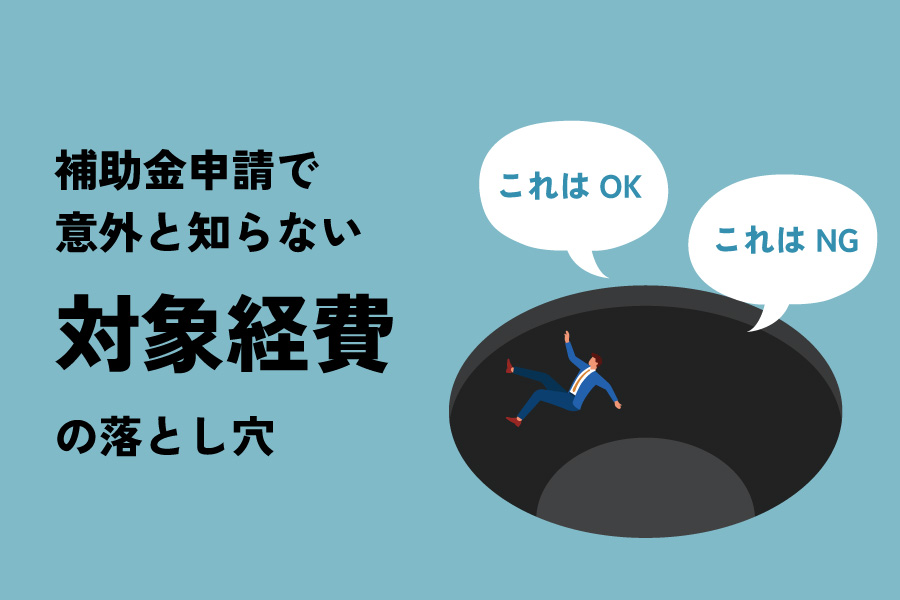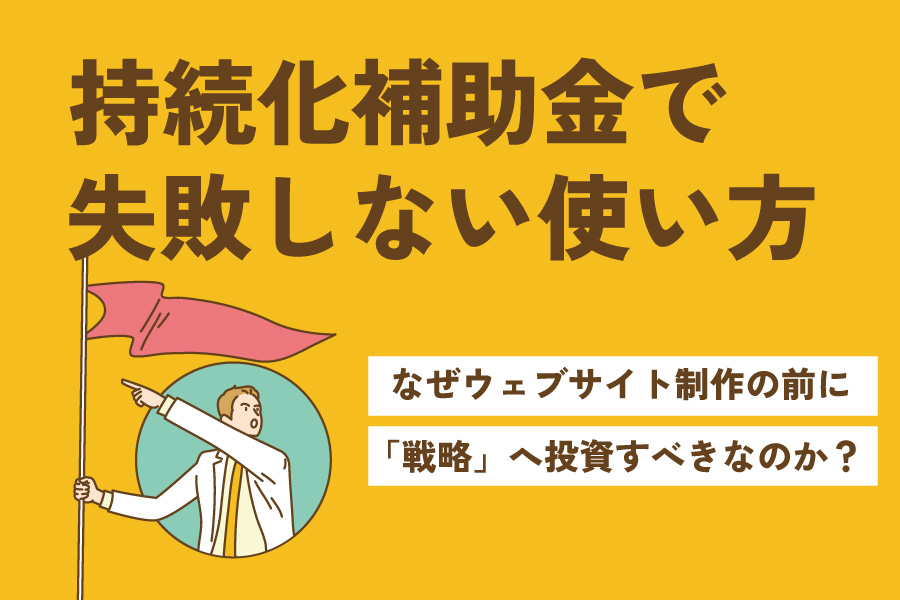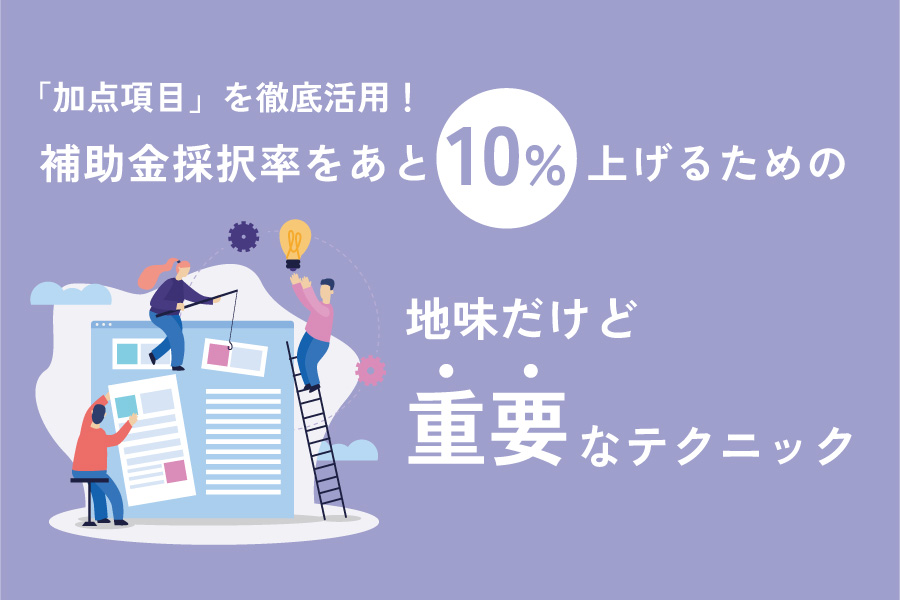
同じ補助金に申請したA社とB社。どちらも甲乙つけがたい、素晴らしい事業計画書を提出しました。
しかし、採択されたのはA社だけでした。この差は、どこで生まれたのでしょうか?
その答えは、多くの場合「加点項目」にあります。
補助金申請において、「加点項目」は“取れたらラッキーなボーナスポイント”などでは断じてありません。ライバルと僅差の勝負を繰り広げる今日の補助金レースにおいて、これらは採択を掴むために、ほぼ“必須”の戦略的要素です。
この記事では、なぜ加点が必須なのか、そして、いかにしてそれらを計画的に獲得していくか、その地味で重要なテクニックを解説します。
1. なぜ「加点」が、今や“必須”なのか? ― 合格ラインと採択ラインの違い
加点の重要性を理解するために、大学受験をイメージしてみてください。
- 事業計画書の中身(事業の新規性や成長性):これは、英語や数学といった主要科目の点数です。ここで高得点を取ることは、まず「合格ライン」を超えるための絶対条件です。
- 加点項目:これは、英検や部活動の実績といった「内申点」や「ボーナス点」です。
人気の大学では、多くの受験生が主要科目で高得点を取って「合格ライン」にひしめき合っています。その中で、実際に「入学(=採択)」できる一握りを決めるのは、まさにこの「内申点」の差です。
補助金も全く同じです。特に人気の補助金では、「素晴らしい事業計画書」はもはや当たり前。その上で、ライバルより頭一つ抜け出し、「採択ライン」を突破するために、加点の積み上げが不可欠なのです。
2. “付け焼き刃”では取れない。「戦略」と連動した加点項目の積み上げ方
「それなら、申請直前に取れる加点を、急いで取ればいい」と考えるのは、最も危険な間違いです。
なぜなら、影響の大きい加点項目の多くは、取得までに数ヶ月単位の準備期間を要するものや、日頃の経営姿勢そのものが問われるものばかりだからです。
付け焼き刃で取り繕うのではなく、中長期的な経営戦略の一環として、計画的に取得を目指す。
この姿勢が、結果として採択率を大きく引き上げます。
3. 主要な加点項目と、その「本当の意味」
補助金によって加点項目は異なりますが、多くの補助金で共通して評価される主要な項目と、その「戦略的な意味」を理解しましょう。
- 経営革新計画の承認:これは、単なる「計画書」ではありません。3〜5年の中長期的な経営計画を策定し、都道府県から「革新的な取り組みである」と承認を受けるプロセスです。この策定プロセス自体が、補助金申請に向けた、最高の予行演習となります。
- パートナーシップ構築宣言:これは、下請企業など取引先との公正な関係を築くことを、会社の代表者名で宣言する制度です。目先の利益だけでなく、サプライチェーン全体での共存共栄を目指すという、企業の高い倫理観と社会的責任を示す強力なアピールになります。
- 事業継続力強化計画(BCP)の認定:自然災害やサイバー攻撃といった、不測の事態に備えるための計画です。この計画を立てることは、自社の事業の弱点やリスクを客観的に洗い出すことに繋がります。つまり、リスク管理能力の高い、揺るぎない経営基盤を持つ企業であることの証明となるのです。
- 大幅な賃上げ計画の表明:従業員への高い水準の賃上げを計画・表明することは、「私たちの事業は、これだけの利益成長を達成できる」という、経営者の強烈な自信の表れとして、審査官にポジティブな印象を与えます。
4. FSPが「加点の取りこぼし」を防げる理由
私たちFSPの支援は、単に事業計画書を作成することから始まりません。まず、クライアントの事業の根幹にある課題と向き合い、未来への「価値の旗」を共に打ち立てることからスタートします。
この深い戦略策定のプロセスを経るからこそ、「貴社の場合は、まず経営革新計画の承認を目指しましょう」「この取り組みは、パートナーシップ構築宣言に繋がりますね」といった、長期的視点での加点戦略を、自然な形で提案し、実行に移すことができるのです。
申請直前に慌てるのではなく、経営戦略の当然の帰結として、加点を積み上げていく。
これがFSPのスタイルです。
まとめ
補助金採択の世界では、「良い計画」を出すだけでは、もはや勝てません。
「良い計画」に、どれだけ多くの「加点」を上乗せできるか。この総力戦で、採択の可否が決まります。
加点項目は、申請のための「作業」ではありません。
それぞれが、あなたの会社をより強く、より魅力的にするための「経営戦略」そのものです。
ぜひ、これらの項目を自社の経営計画に積極的に取り入れ、ライバルに差をつける、確かな一歩を踏み出してください。


まずは「無料個別戦略診断」で、
現状と可能性を客観的に見つめ直すことから始めてみましょう 。