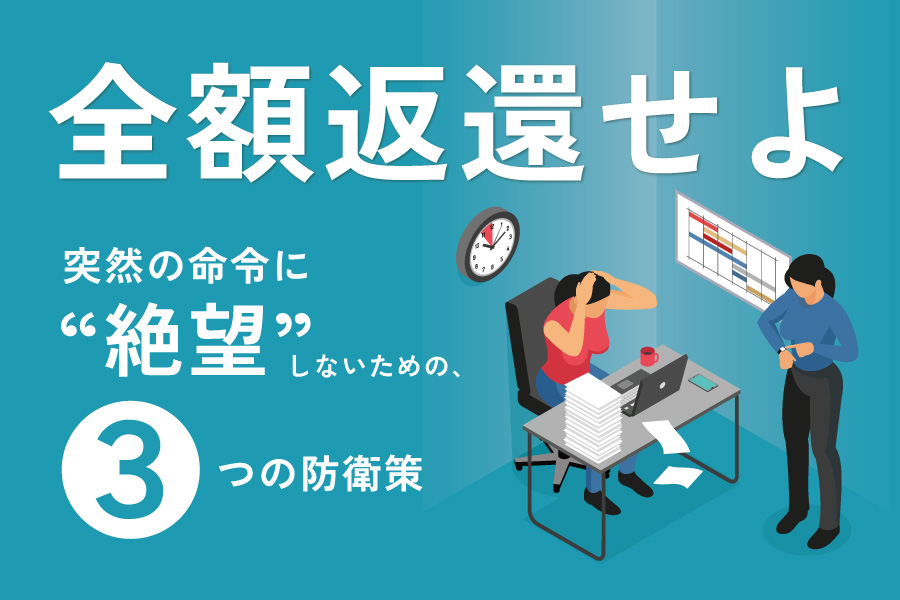
補助金の入金も無事に終わり、事業も軌道に乗ってきた数年後、あなたの会社に一通の封書が届く。
「会計検査院による実地検査のお知らせ」、そして、その先に待っているかもしれない「補助金返還命令」。
これは、決して大げさな話ではありません。
補助金は、国民の税金を原資としているため、その使途については、事業期間中はもちろん、終了後数年間にわたって、極めて厳格なチェックが行われます。
ルールを一つでも破れば、「補助金を返還せよ」という、経営を根幹から揺るがす事態に陥りかねません。
この記事では、そうした最悪の事態を招く典型的なケースと、返還命令から会社を守るための絶対的な防衛策を解説します。
なぜ「返還命令」は、突然やってくるのか?
補助金のルールは、申請書を提出した「公募要領」と、採択後に送られてくる「交付規程」に全て書かれています。
これらのルールに違反していないかをチェックするのが、国が行う「会計検査」です。
この検査は、補助事業が終了して3年後、5年後といった、経営者が油断した頃に、予告なく行われることもあります。
そして、そこで違反が見つかると、補助金の返還、場合によっては加算金を上乗せしての返還を命じられるのです。
「返還」に繋がりかねない、3つの重大な違反ケース
ケース①:事業の失敗・廃業
これが、最も悲劇的で、かつ深刻なケースです。
補助金を活用した事業がうまくいかず、やむなく廃業を選択した場合、購入した資産の「残存簿価」に応じて、受け取った補助金の一部を現金で返還する義務が生じます。
財務状況が最も悪化した、まさにその瞬間に、多額の現金返済という追い打ちがかかる、致命的なメカニズムです。
ケース②:補助金の目的外利用
これは、「計画書に書いたこと“以外”に、補助金を使ってしまう」ケースです。
- 「少し資金が余ったから、運転資金に回そう」
- 「計画していたAという機械より、Bという機械の方が良さそうだから、勝手に変更して購入した」
- 「パソコン購入の予定はなかったが、経費として申請してしまった」
これらは全て、重大なルール違反です。補助金は、採択された事業計画を、一言一句たがわずに実行するためにのみ、使うことが許されています。
ケース③:資産の無断処分
補助金で購入した機械や設備などの資産には、「財産処分制限期間」(例えば、機械装置なら5年間など)が定められています。この期間内に、国の承認を得ずに、その資産を「売却する」「他社に貸し出す」「担保に入れる」といった行為は、固く禁じられています。
これは、「その資産を活用して、長期間にわたり、地域経済や日本の産業に貢献してくださいね」という、国との約束だからです。
「返還命令」を回避するための、絶対的な防衛策
これらの恐ろしい返還命令から、会社を守るための防衛策は、実は非常にシンプルです。
それは、「公募要領と交付規程を、自社の経理・法務のルールブックとして、徹底的に遵守すること」に尽きます。
しかし、多忙な経営者が、数百ページにも及ぶこれらの書類を完璧に理解し、数年間にわたって全てのルールを遵守し続けるのは、至難の業です。
だからこそ、私たちFSPは、補助金の「採択」をゴールとは考えません。
採択後の、この長く、複雑なコンプライアンス期間においても、クライアントが道を踏み外さないように、計画の実行から、各種報告、そして会計検査の備えまで、継続的にサポートし続けること。それこそが、FSPが考える「伴走支援」の本当の価値なのです。
まとめ
補助金は、決して「もらって終わりの打ち出の小槌」ではありません。
それは、国民の税金という重みを背負った、国との「長期的な契約」です。
契約書(=公募要領・交付規程)を熟知し、そのルールを誠実に守り続けること。そして、その実行が難しいと感じるのであれば、ルールを熟知した専門家をパートナーにつけること。
その地道なコンプライアンス意識こそが、「突然の返還命令」という最大の恐怖から、あなたの会社を守る、唯一にして最強の防衛策なのです。


まずは「無料個別戦略診断」で、
現状と可能性を客観的に見つめ直すことから始めてみましょう 。
