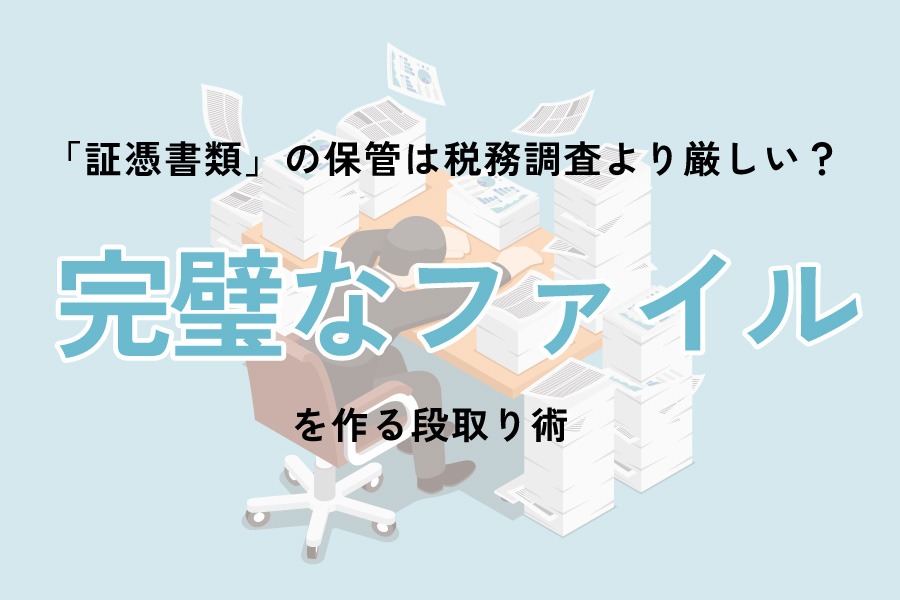
「税務調査は、問題なくクリアできた。だから、補助金の経理も大丈夫だろう」 もし、あなたがそう考えているとしたら、それは非常に危険なサインかもしれません。
補助金事業の経費に関するチェック、特に、その根拠となる証憑書類(見積書や請求書、振込明細など)の管理に求められるレベルは、多くの経営者様の想像を超えて、“税務調査よりも厳しい”と言っても過言ではないからです。
この記事では、なぜ補助金監査がそれほどまでに厳しいのか、その理由と、後から「この経費は認められません」という悲劇を防ぐための、具体的な書類保管の「段取り術」を解説します。
なぜ、補助金監査は“税務調査より厳しい”のか?
税務調査と補助金監査では、審査官が見ている「視点」が、根本的に異なります。
- 税務調査の視点
「その経費は、事業の経費として、正当か?」 主に、売上と経費の対応関係や、私的な支出が混じっていないか、といった点がチェックされます。 - 補助金監査の視点
「その経費は、事業の経費として正当、かつ、承認された計画書通り、かつ、全てのルールに則っているか?」 補助金監査では、この“三重のチェック”が行われます。たとえ正当な事業の経費であっても、それが採択された事業計画書の内容と1円でも違っていたり、定められたルール(例:相殺の禁止など)から僅かでも外れていたりすれば、容赦なく「不適切」と判断されてしまうのです。
「完璧な証憑ファイル」を作るための、具体的な保管方法
この厳しいチェックをクリアするためには、事業が始まったその日から、計画的かつ体系的に証憑書類を保管しておく「段取り」が不可欠です。
FSPが推奨する保管術:取引ごとの“一気通貫ファイリング”
補助金事業専用の、大きなファイル(バインダー)を用意しましょう。
そして、一つの取引(例:A社からの機械購入)ごとに、以下の書類を、物語が流れるように、時系列の順番でファイリングしていきます。
- 見積書(申請時に提出したものと同じもの)
- 発注書・契約書(日付が見積書より後であること)
- 納品書(日付が発注書・契約書より後であること)
- 請求書(日付が納品書と同じか、後であること)
- 銀行の振込明細(支払った証拠。日付が請求書より後であること)
- 写真(納品・設置された資産の写真。資産に貼付された補助金シールも見えるように)
この「取引のストーリー」が一つの束で完結しており、かつ、全ての書類の「日付」「金額」「品名」「宛名」に一切の矛盾がない状態。これこそが、審査官が一目見て「適切に執行されている」と判断できる、「完璧な証憑ファイル」です。
「いつまで保管すべき?」― 答えは“交付規程”にあり
では、この完璧なファイルは、いつまで保管すれば良いのでしょうか。
税法では、帳簿書類の保管期間は原則7年間(欠損金がある場合は10年間)と定められています。補助金の場合、これと同等か、それ以上の期間を求められることが一般的です。
多くの主要な補助金では、「補助事業が完了した年度の終了後、5年間」の保管を義務付けています。
しかし、これはあくまで一般的な目安です。正確な保管期間は、必ず、採択後に送られてくる「交付規程」という書類に明記されています。この書類を正しく読み解き、定められた期間、確実に保管し続ける必要があります。会計検査院の実地検査は、事業終了後、数年経ってから行われることも珍しくありません。
まとめ
補助金事業における証憑書類の保管は、単なる経理作業ではありません。それは、国民の税金という貴重な資源を預かる事業者としての、「説明責任」を果たすための、極めて重要なプロジェクトマネジメントです。
「税務調査でOKだったから」という甘い考えは、通用しません。
事業が始まったその日から、補助金監査の厳しい視点を常に意識し、完璧な証拠書類を積み上げていく。
その地道な「段取り」こそが、採択後のあなたの会社を、最大のリスクから守る防波堤となるのです。


まずは「無料個別戦略診断」で、
現状と可能性を客観的に見つめ直すことから始めてみましょう 。
