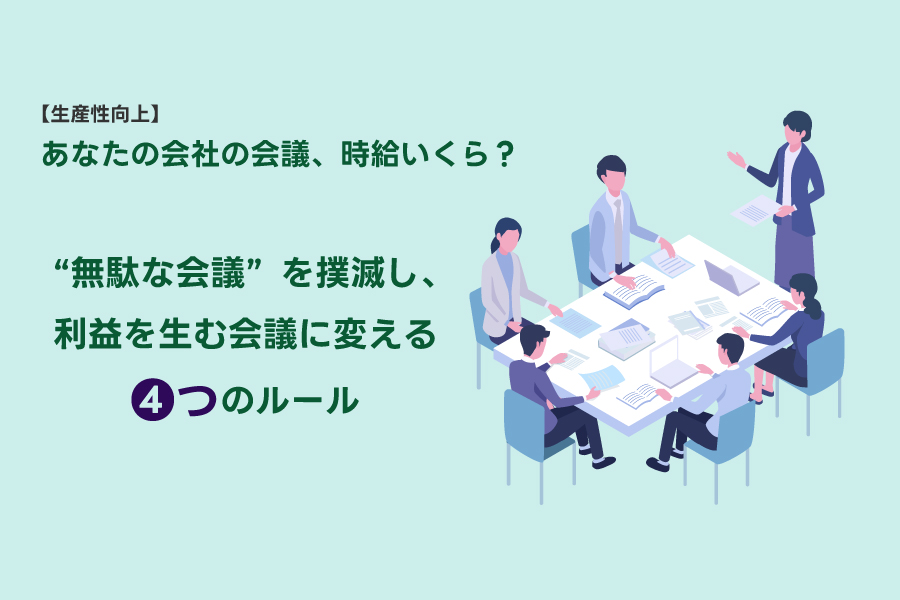
目的が分からないまま、ダラダラと続く会議。発言するのは、いつも同じメンバー。そして、会議が終わった後には、「で、結局、何が決まったんだっけ?」という、虚無感だけが残る…。
もし、あなたの会社で、こんな光景が日常茶飯事だとしたら、それは、極めて深刻な経営課題です。なぜなら、会議は、従業員の“時給”を消費して行われる、コストのかかる経営活動だからです。
時給2,500円の社員5人が、2時間の無駄な会議をすれば、それだけで25,000円のコストが、泡と消えます。この記事では、この“見えないコスト”を撲滅し、会議を、新たな価値と利益を生み出す、生産的な場へと変えるための、4つのシンプルなルールを解説します。
ルール①:【会議前】「アジェンダ」なき会議は、即刻解散せよ
これが、最も重要で、全ての基本となるルールです。アジェンダ(議題書)が、事前に共有されていない会議は、原則として、開催してはいけません。
優れたアジェンダには、必ず3つの要素が含まれています。
- 会議の「目的」:この会議は、「情報共有」なのか、「アイデア出し」なのか、それとも「意思決定」なのか。
- 会議の「ゴール」:会議が終わった時に、「どういう状態になっていれば成功か」が、具体的に書かれている。(例:「〇〇の件について、A案かB案かを決定する」)
- 議題ごとの「時間配分」:どの議題に、何分かけるのかが、明確になっている。
この事前準備(=段取り)こそが、会議という船が、目的地を見失い、漂流することを防ぐ、唯一の羅針盤です。
ルール②:【会議中】「決定者」と「決定方法」を、最初に宣言せよ
会議が“長引く”最大の原因。それは、「どうやって結論を出すのか」という、意思決定のルールが、曖昧なまま、議論が進んでしまうことです。
会議の冒頭で、ファシリテーター(進行役)は、必ず以下を宣言しましょう。 「本日のこの議題に関する最終的な意思決定は、〇〇部長が行います」 「この件は、多数決で決めたいと思います」 「今日は、決定はせず、アイデアを出すことだけがゴールです」
誰が、どうやって決めるのかを、最初に全員で共有することで、議論は着地点を見失わず、驚くほど生産的になります。
ルール③:【会議中】“脱線”を恐れず、しかし“迷子”は許すな
活発な会議では、議論が白熱し、話が“脱線”することもあります。それは、新しいアイデアが生まれる、良い兆候かもしれません。
しかし、ファシリテーターの重要な役割は、その脱線が、単なる“迷子”にならないように、議論を、アジェンダという本筋に、引き戻すことです。
「〇〇さん、非常に興味深い論点ですが、その話は、次の議題で改めて議論しませんか。まずは、△△の件を、あと5分で結論付けましょう」 このように、軌道修正をすることで、会議は、活気を失うことなく、時間内にゴールへとたどり着くことができます。
ルール④:【会議後】「議事録」と「ToDoリスト」を、24時間以内に共有せよ
会議は、終わった瞬間に、その価値の9割が失われる、と言っても過言ではありません。なぜなら、人は忘れる生き物だからです。会議の価値を、未来の行動へと繋げるために、議事録の共有を、24時間以内に徹底しましょう。
そして、その議事録で、最も重要な項目が「ToDoリスト」です。
- 決定事項:何が決まったか
- ToDo:誰が、何を、いつまでにやるか
- 保留事項:次に議論すべきことは何か
この「ToDo」が明確になって初めて、会議は、具体的な“次の一歩”を生み出し、会社を前に進めるエンジンとなるのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。無駄な会議をなくすためのルールは、決して難しいものではありません。それは、少しの「準備(段取り)」と、「規律」の問題です。
会議の質は、その会社の「組織文化」そのものを、映し出す鏡です。 明確な目的(=想いの糸)を持ち、社員一人ひとりが、自らの役割と責任(=行動の糸)を自覚している会社では、会議は、自然と、短く、そして生産的になります。
あなたの会社の、明日の会議から、ぜひ、この4つのルールを、試してみてください。


まずは「無料個別戦略診断」で、
現状と可能性を客観的に見つめ直すことから始めてみましょう 。
