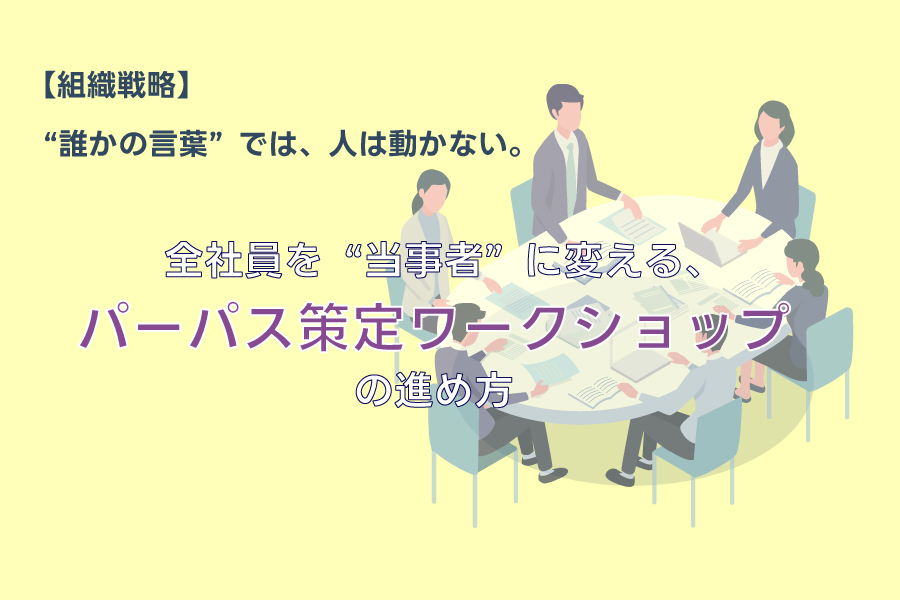
「我が社のパーパスは、これだ!」 社長であるあなたが、一人で考え抜いた、素晴らしいパーパス。しかし、それを、社員に一方的に“お披露目”しただけでは、残念ながら、組織は、同じ方向を向くことはありません。
なぜなら、それは、社員にとって、どこか他人事の“誰かの言葉”でしかないからです。
社員一人ひとりの心を動かし、組織全体の羅針盤となる「生きたパーパス」を創るために、最も効果的な方法。それが、全社員を巻き込んだ「パーパス策定ワークショップ」です。この記事では、その具体的な進め方を、3つのステップで解説します。
なぜ「ワークショップ」という“面倒”な手法を取るのか?
「全社員を集めて、話し合うなんて、時間がかかって、面倒だ」と感じるかもしれません。しかし、この一見“面倒”なプロセスにこそ、計り知れない価値があります。
- 当事者意識が生まれるから 人は、自らが関わって創り上げたものを、大切にし、守り、育てようとします。ワークショップを通じて、社員一人ひとりが「これは、“私たちが”創ったパーパスだ」と感じること。この当事者意識こそが、理念浸透の、最大のエンジンとなります。
- 現場に眠る“宝”が、見つかるから 会社の本当の価値や強みは、社長室ではなく、日々、お客様と接している「現場」にこそ、眠っています。ワークショップは、そうした、社員一人ひとりの経験の中に眠る“宝”を、掘り起こす、最高の機会なのです。
パーパス策定ワークショップ、3つのステップ
私たちFSPが、クライアントと共に実践している「想いの糸」を紡ぎ出すプロセスは、まさに、このワークショップそのものです。
【STEP 1:準備編】“お宝”のありかを探る(事前アンケート)
いきなり集まって「さあ、話し合え」では、良い意見は出てきません。ワークショップの前に、全社員を対象とした、匿名のアンケートを実施しましょう。
<質問例>
- 「この会社で働いていて、一番『誇り』を感じた瞬間は、どんな時ですか?」
- 「お客様から、一番『ありがとう』と言われた仕事は、何でしたか?」
- 「もし、私たちの会社が一人の人間だとしたら、どんな性格の人だと思いますか?」
このアンケートが、社員の頭と心を、ほぐす準備運動となり、議論のきっかけを作ります。
【STEP 2:実践編】“お宝”を掘り起こし、磨き上げる(ワークショップ当日)
いよいよ、ワークショップ本番です。重要なのは、役職や部署に関係なく、誰もが、安心して、本音で話せる「心理的に安全な場」を作ることです。
- お宝の共有:まず、事前アンケートの結果を、全員で共有します。
- お宝の深掘り:数名の小グループに分かれ、「なぜ、その瞬間に、誇りを感じたのか?」といった、アンケートの答えの背景にある「物語」を、互いに語り合います。
- お宝の抽出:各グループで語られた物語の中から、「これぞ、うちの会社らしさだ」という、キーワードや、価値観を、付箋などに書き出していきます。
【STEP 3:言語化編】“お宝”に、名前を付ける(パーパス・ステートメントの作成)
ワークショップで、たくさんの“お宝の原石”が集まったら、最後に、それを、一つの輝く宝石へと、磨き上げていきます。
- 経営陣による、言葉の彫琢:経営陣が、ワークショップで出てきたキーワードや物語を元に、パーパス、ビジョン、バリューといった「理念体系」の草案を作成します。
- 全社員への、フィードバック:そして、最も重要なのが、その草案を、必ず、全社員に、もう一度、共有することです。「みんなで掘り起こした宝は、こういう言葉になりました。これは、私たちの想いを、代弁していますか?」と。
この最終確認のプロセスを経て、パーパスは、名実ともに「全社員の、生きた言葉」となるのです。
まとめ
会社のパーパス(存在意義)は、経営者が、一人、書斎で、作り上げるものではありません。 それは、全社員の、これまでの仕事の中に、すでに、欠片として存在している“宝”を、みんなで、もう一度、発見し、磨き上げる、共同作業なのです。
この、対話と、共感に満ちたプロセスを経て、創り上げられたパーパスだからこそ、社員一人ひとりの日々の仕事の「拠り所」となり、会社という船を、同じ未来へと、力強く、推し進めていくのです。


まずは「無料個別戦略診断」で、
現状と可能性を客観的に見つめ直すことから始めてみましょう 。
