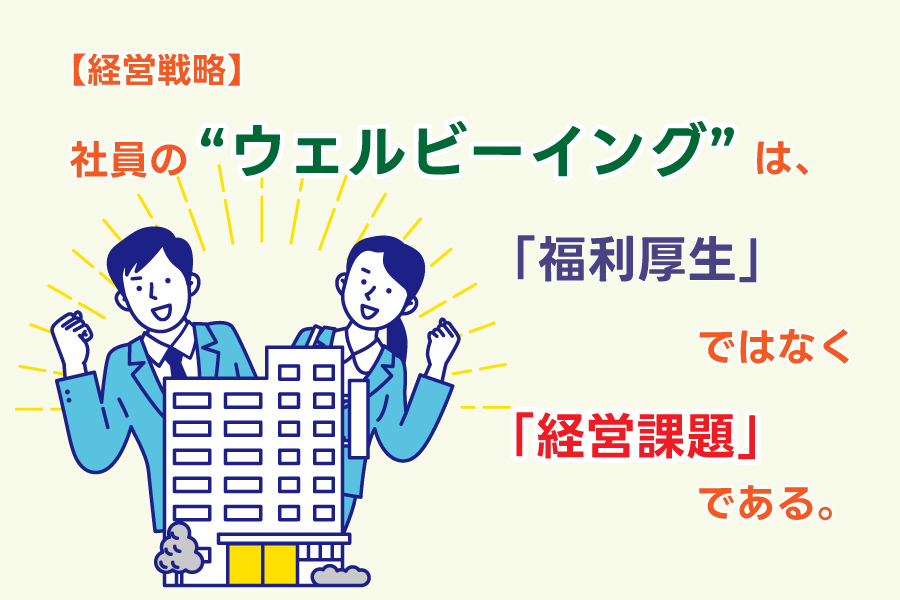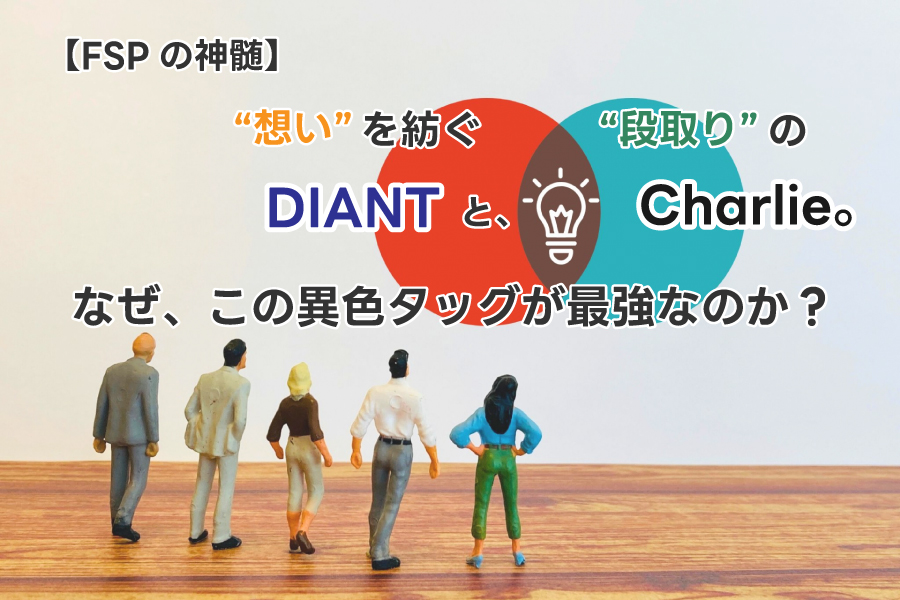「補助金を使って開発した新商品が、予想を遥かに超えて大ヒットした!」 経営者として、これほど嬉しいことはないでしょう。
しかしその時、ふとこんな怖い噂を耳にすることはありませんか?
「補助金事業で、利益が出すぎると、国にお金を返さなければならないらしい…」
成功を喜ぶべき状況で、なぜか不安がよぎる。
この噂の正体が、補助金のルールの一つである「収益納付」です。
この記事では、この「収益納付」とは一体何なのか、そのルールと、私たちが考える「本当の危険性」、そして、経営者が取るべき正しい姿勢について解説します。
「収益納付」とは?― 補助金における“成功報酬”のようなルール
まず、言葉の定義と、大前提を整理しましょう。
「収益納付」とは、補助金を活用して開発した製品やサービス(=補助事業)そのものから、事業期間終了後、“直接的に”収益が発生し、かつ、その累計収益額が、投資した総額(自己負担額+補助金額)を上回るほど、非常に大きな利益が出た場合に、その利益の一部を、受け取った補助金を上限として国に納付(返還)するというルールです。
【絶対に知っておくべき大前提】
- 全ての補助金にあるルールではない:主に、新製品開発や研究開発(R&D)を対象とした補助金に適用されることが多いです。
- 会社の利益全体が対象ではない:あくまで、補助金で開発した「その事業」から直接生まれた収益だけが対象です。
- 「罰金」ではない:「補助金返還」がルール違反に対する罰則であるのに対し、「収益納付」は、事業が大成功した結果として発生するものです。
つまり、これは一種の“成功報酬”に近いルールなのです。
“収益納付”の本当の「危険性」とは何か?
「なんだ、大成功した場合だけなら、心配ないか」と考えるのは、まだ早いかもしれません。
私たちが考える「収益納付」の本当の危険性は、その制度自体にあるのではありません。
本当の危険性。それは、「収益納付を恐れるあまり、経営者の挑戦意欲に“心理的なブレーキ”がかかってしまうこと」です。
「あまり儲けすぎると、お金を返さなければならないなら…」
- 商品の価格を、少し安めに設定してしまう
- 積極的な広告宣伝や、販路開拓の手を緩めてしまう
- 無意識のうちに、そこそこの成功で満足しようとしてしまう
これこそが、本末転倒の悲劇です。
補助金は、企業の飛躍的な成長(=大きな利益)を後押しするためにあるはずなのに、そのルールを恐れるあまり、自ら成長の可能性に蓋をしてしまう。この経営マインドの萎縮こそが、最大の「危険性」なのです。
FSPが提唱する「収益納付」との正しい向き合い方
では、経営者は、このルールとどう向き合うべきなのでしょうか。
私たちFSPは、クライアントに常にこうお伝えしています。
「収益納付は、ペナルティではなく、“成功の勲章”です。だからこそ、本気で収益納付を目指しにいきましょう」と。
- 思考の転換:収益納付を「恐れるべきもの」から、「目標とすべきもの」へと、思考を180度転換する。
- 計画への織り込み:事業計画を立てる段階から、「これだけ大きな成功を収め、収益納付を達成します」と、堂々と宣言するくらいの、高い目標を掲げる。
- 「稼ぐ力」の最大化:小手先の利益調整など考えず、FSPの神髄であるブランディングによる「稼ぐ力」の構築に、全精力を注ぎ込む。
収益納付が発生するほどの成功を収めることができれば、たとえ補助金の一部を国に納付したとしても、それを遥かに上回る利益が、あなたの会社には残ります。
そして何より、「国民の税金を活用し、これだけの経済的成功を生み出した」という事実は、企業の信頼性を飛躍的に高める、最高の勲章となるのです。
まとめ
「利益が出たら返還」というルールは、確かに存在します。
しかし、それは罰金ではありません。あなたの事業が、国の期待を大きく超える大成功を収めた証です。
そのルールを恐れて、挑戦から逃げないでください。中途半端な成功を目指さないでください。
私たちFSPは、クライアントが「収益納付、達成しました!」と、胸を張って報告してくれることこそが、私たちの支援が成功した証だと考えています。恐れずに、大きな成功を、共に掴み取りにいきましょう。


まずは「無料個別戦略診断」で、
現状と可能性を客観的に見つめ直すことから始めてみましょう 。