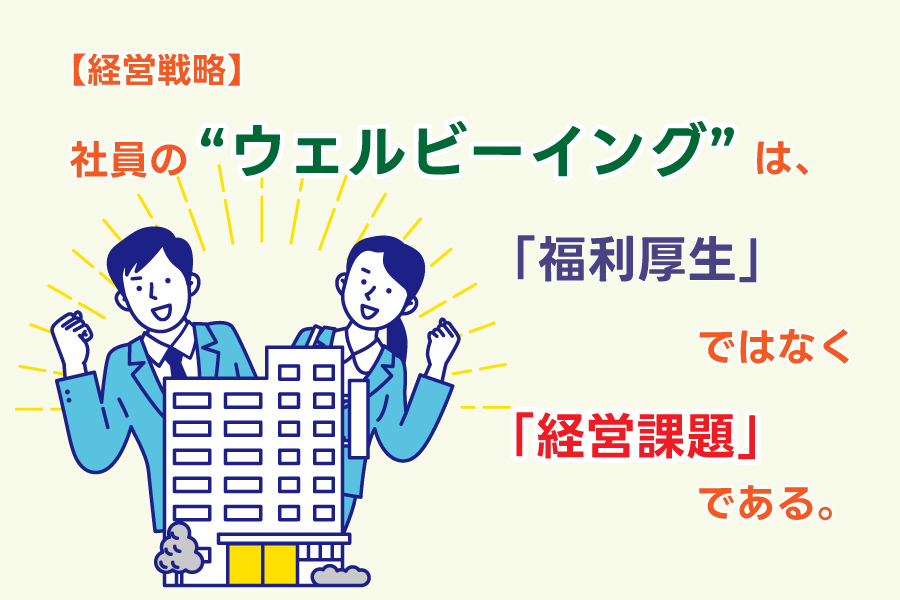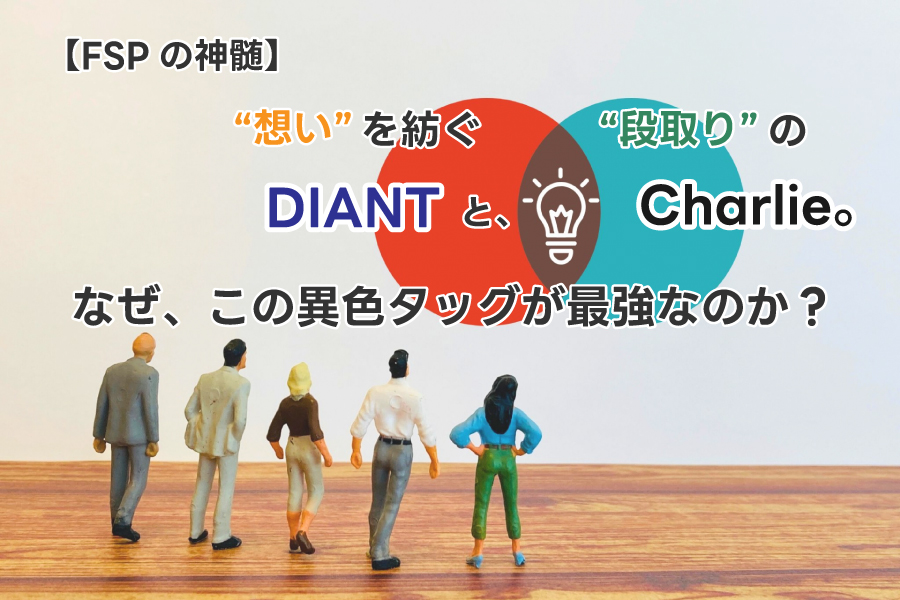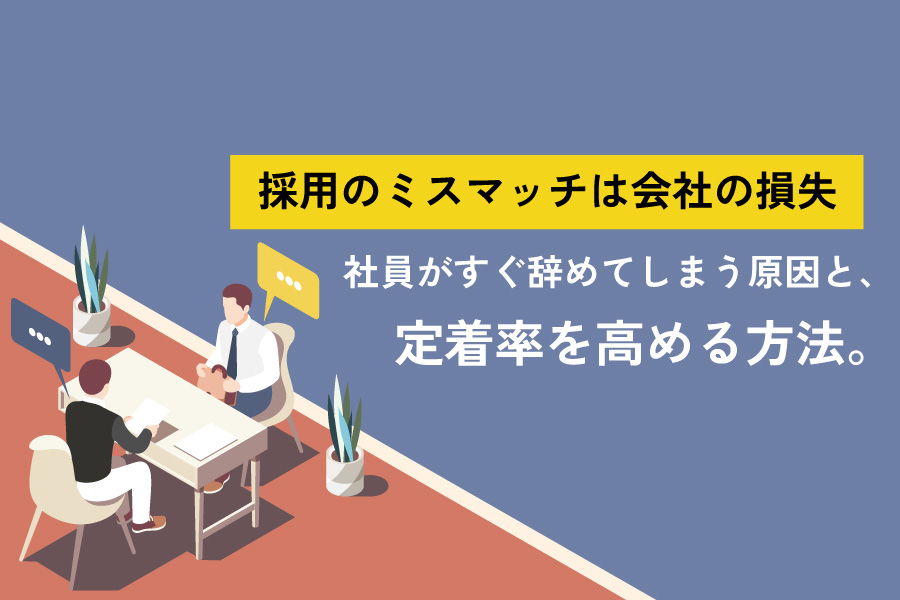
多額のコストと時間をかけて採用し、ようやく育て始めた新入社員が、入社から数ヶ月で辞めてしまう…。
この「採用ミスマッチ」は、経営者の心を折るだけでなく、会社の体力を静かに、しかし確実に奪っていく“静かな出血”です。
一人、また一人と社員が辞めていくたびに、あなたの会社は、目に見えない多大な損失を被っているのです。
なぜ、ミスマッチは起きてしまうのでしょうか。そして、この出血を止めるためには、何が必要なのでしょうか。
この記事では、その根本原因と、社員の定着率を高めるための本質的な方法について解説します。
採用ミスマッチがもたらす、深刻な「経営損失」
まず、新入社員が一人辞めることで、会社がどれだけの損失を被るか、具体的に見てみましょう。
- 直接的コスト:支払った求人広告費、人材紹介会社への手数料など、採用活動にかかった費用が、全て無駄になります。
- 間接的コスト:その社員にかけた研修費用、教育担当者や上司が費やした時間、そして、再び採用活動を始めるためのコストと時間。さらに、他の社員のモチベーション低下といった、数字に表れにくい損失も発生します。
これらを合計すると、早期離職による損失は、その社員の年収の50%〜100%に相当するとも言われています。これは、決して無視できない、深刻な経営損失です。
なぜミスマッチは起きるのか?― 入社後に発覚する「3つのズレ」
では、なぜ時間とお金をかけた選考でも、ミスマッチは起きてしまうのでしょうか。
それは、入社前に聞いていた「期待」と、入社後の「現実」の間に、埋めがたい「3つのズレ」が存在するからです。
①「価値観」のズレ
旗のデザインは好きだったけど、向かう先が違った 求職者は、ウェブサイトのデザインや、オフィスの雰囲気に惹かれて入社します。しかし、働き始めてから、会社の本当の「理念・ビジョン(=想いの糸)」が、自分の価値観と合わないことに気づきます。会社の向かう先に共感できなければ、働くモチベーションは維持できません。
②「文化・風土」のズレ
言っていることと、やっていることが違う 面接では「風通しが良く、若手もどんどん挑戦できる社風です」と聞いていた。しかし、実際に入社してみると、トップダウンで、失敗が許されない、息苦しい空気が流れていた。これは、会社の掲げる理念が、社員の日々の「行動(=行動の糸)」にまで落とし込まれていない、典型的な「絵に描いた餅」の状態です。
③「人間関係」のズレ
仲間として、迎え入れられていない 入社後、誰に相談すれば良いのか分からず、放置されてしまう。質問しても、忙しそうにされて、話しかけづらい。新しい環境で、たった一人、孤立してしまう。これは、会社が、新入社員との「絆(=紡ぎ方の糸)」を、意識的に築こうとしていない場合に起こります。
「定着率」を高めるための、FSP流の処方箋
これらの「3つのズレ」をなくし、定着率を高めるためには、採用活動と、入社後の受け入れ体制を、一貫した戦略のもとで再構築する必要があります。
処方箋①:採用の段階で「パーパス(想いの糸)」を、正直に、そして熱く語る
良いことばかりを言うのではなく、自社の「理念・ビジョン」を、ありのままに伝えましょう。「私たちは、何のために存在するのか」「どんな未来を目指しているのか」。その旗に心から共感してくれる人だけを、仲間として迎え入れる。この“入り口”のフィルタリングが、ミスマッチを防ぐ最大の鍵です。
処方箋②:「行動指針(クレド)」を創り、全社で実践する
理念という抽象的な言葉を、「私たちは、お客様に対して、このように行動します」という、具体的な「行動指針(=行動の糸)」にまで落とし込み、全社員で共有・実践します。これにより、会社の「文化・風土」に一貫性が生まれ、「言っていることと、やっていることが違う」というズレを防ぎます。
処方箋③:「オンボーディング」の仕組みを設計する
新入社員を、暖かく迎え入れ、組織の一員として早期に戦力化するための、計画的な受け入れプログラム(オンボーディング)を設計します。最初の90日間で、誰が、何を、どのように教えるのか。誰が、精神的なサポートをするのか。この「絆づくり(=紡ぎ方の糸)」の仕組みが、新入社員の孤独を防ぎ、エンゲージメントを高めます。
まとめ
社員の定着率は、運や偶然で決まるものではありません。それは、採用から入社後までの一貫した「戦略」の結果です。
会社の「価値観」を正直に伝え、 その価値観に基づいた「行動」を、全社で実践し、 新しい仲間を、大切に育む「関係性」を築く。
この、当たり前で、しかし最も本質的な取り組みこそが、「採用ミスマッチ」という静かな出血を止め、あなたの会社を、人が育ち、辞めない、強い組織へと変えていくのです。そして、これらの一貫した取り組みこそが、FSPがご支援するブランディングの本質であり、採用におけるミスマッチを減らし、定着率向上に貢献すると、私たちが確信する理由です。


まずは「無料個別戦略診断」で、
現状と可能性を客観的に見つめ直すことから始めてみましょう 。