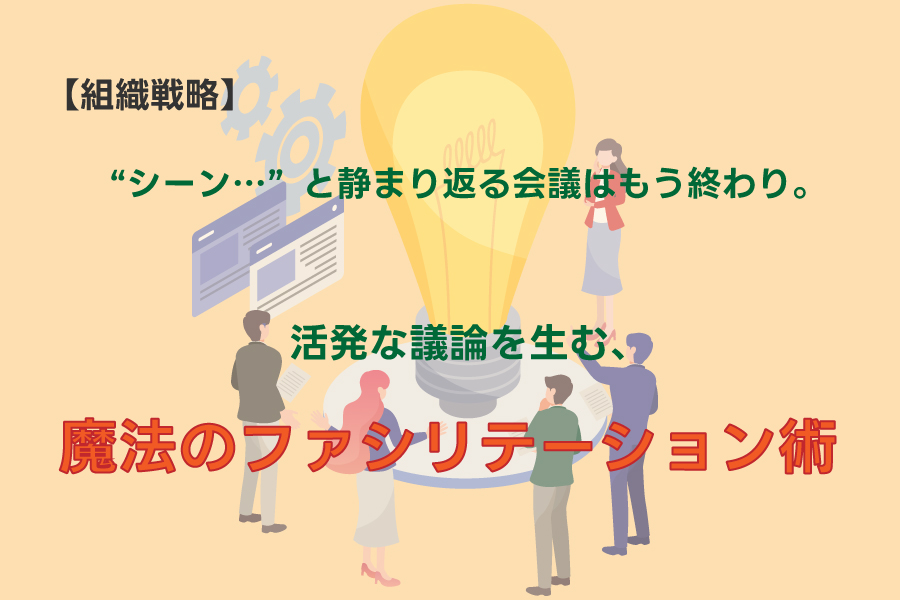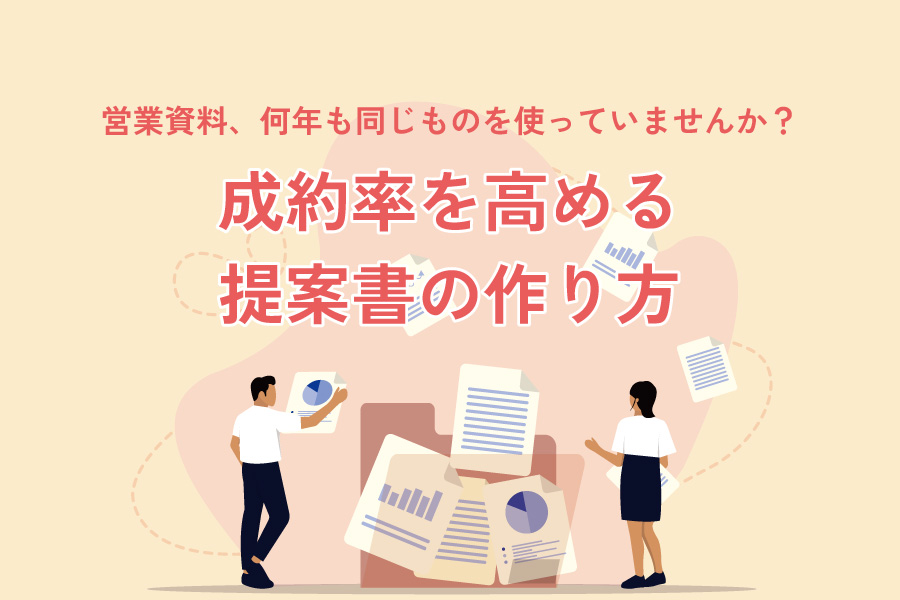
会社のロゴは、10年前のもの。掲載されている商品も、一部はすでに終売している…。
あなたは、そんな“ホコリをかぶった”営業資料や提案書を、今日も大切なお客様との商談で、使ってしまってはいないでしょうか。
多くの経営者様が、日々の業務に追われ、営業資料のアップデートを後回しにしがちです。
しかし、その古い資料こそが、あなたの会社の素晴らしい価値が、お客様に全く伝わらない
“最大の原因”なのかもしれません。
この記事では、あなたの会社の営業資料を、一方的な“独り言”から、お客様の心を動かす“対話”のツールへと変え、成約率を劇的に高めるための、新しい作り方を解説します。
なぜ、あなたの「営業資料」は、顧客の心に響かないのか?
まず、多くの会社が使いがちな、響かない営業資料の典型的な「構成」を見てみましょう。
- 会社概要:「私たちの会社は、創業〇〇年で…」
- 商品・サービス一覧:「私たちの商品には、こんな特長がありまして…」
- 価格表:「お値段は、このようになっております」
いかがでしょうか。この構成の問題点は、徹頭徹尾、主語が「私たち(WE)」になっていることです。これは、お客様を置き去りにした、一方的な“独り言”でしかありません。お客様が本当に聞きたいのは、あなたの会社の話ではなく、「自分の会社(I)の課題を、どう解決してくれるのか?」という、ただ一点なのです。
成約率を高める提案書は「課題解決の物語」である
では、成約率の高い提案書は、どのような構成になっているのでしょうか。
それは、主語を「私たち」から「あなた(お客様)」へと転換し、お客様を主人公とした「課題解決の物語」として、設計されています。私たちFSPが、自らのご提案で実践しているのも、まさにこの構成です。
<成約率を高める、物語の構成>
- 【共感】お客様の「現状」と「課題」の確認
まず、ヒアリングに基づき、「現在、あなたの会社は、このような状況で、このような課題をお持ちですよね?」と、相手の状況を言語化し、深い理解と共感を示します。 - 【原因】なぜ、その課題が起きているのか?(本質的な原因の提示)
次に、「その課題の根本原因は、実は、ここにあります」と、専門家としての視点から、問題の本質を指摘します。 - 【解決】私たちの「提案」が、どう課題を解決できるのか?
ここで初めて、「その根本原因を解決するために、私たちのこのサービスが、このようにお役に立てます」と、自社のサービスを、課題解決の“処方箋”として提示します。 - 【証拠】なぜ、私たちなら、それができるのか?(実績・お客様の声)
「私たちには、これだけの導入実績や、お客様からの喜びの声があります」と、第三者の客観的な評価(=お客様の声)を示し、提案の信頼性を高めます。 - 【行動】未来に向けた、次のステップ
最後に、「もし、この提案にご興味をお持ちいただけましたら、次は、〇〇というステップに進みましょう」と、お客様が次に取るべき行動を、明確に提示します。
「見せ方」も、価値を伝える重要なメッセージ
物語の構成と同じくらい重要なのが、その物語を盛り付ける「器」、つまり、営業資料の「見せ方(デザイン)」です。
どんなに素晴らしい提案も、古臭く、素人感のあるデザインの資料で語られては、その価値は半減してしまいます。
それは、お客様に「この会社は、細部へのこだわりがない、プロフェッショナルではない会社だ」という、
無言のメッセージを送っているのと同じなのです。
会社の価値観(=想いの糸)を反映した、洗練された「顔立ち(=顔立ちの糸)」の営業資料は、あなたの提案の価値と信頼性を、何倍にも高めてくれるのです。
まとめ
あなたの会社の営業資料を、今すぐ、見直してみてください。
それは、あなたの会社の“独り言”になっていませんか?
それとも、お客様を主人公とした、“対話”のツールになっていますか?
営業資料とは、単なる商品説明書ではありません。それは、お客様の課題に寄り添い、信頼関係を築き、共に未来を創るための、極めて戦略的な「コミュニケーションツール」です。
その作り方を変えるだけで、あなたの会社の成約率は、明日から、劇的に変わる可能性を秘めているのです。


まずは「無料個別戦略診断」で、
現状と可能性を客観的に見つめ直すことから始めてみましょう 。