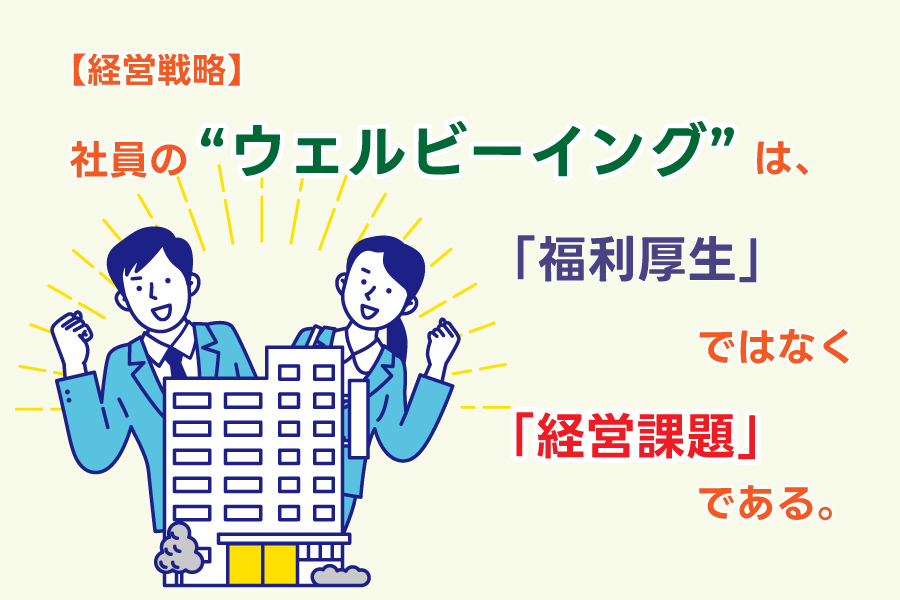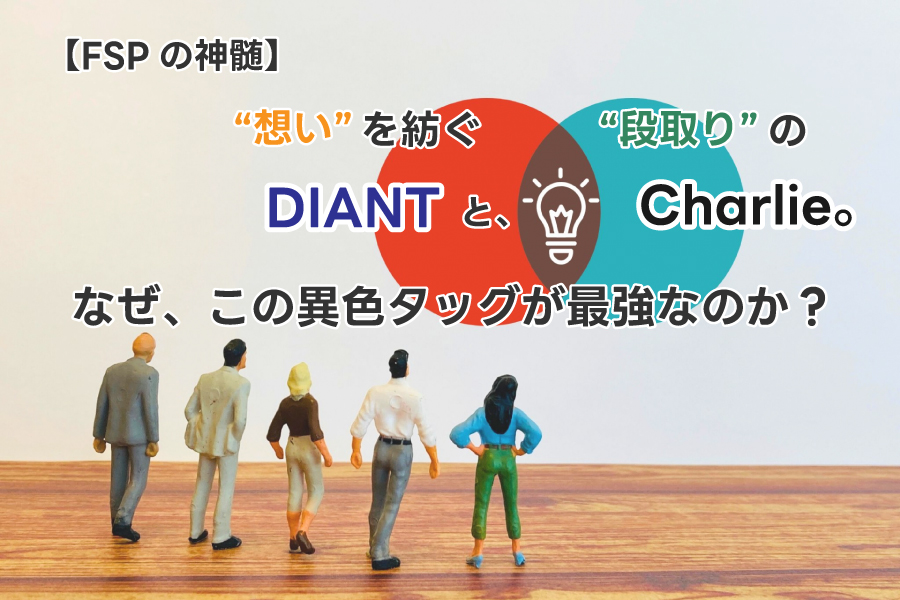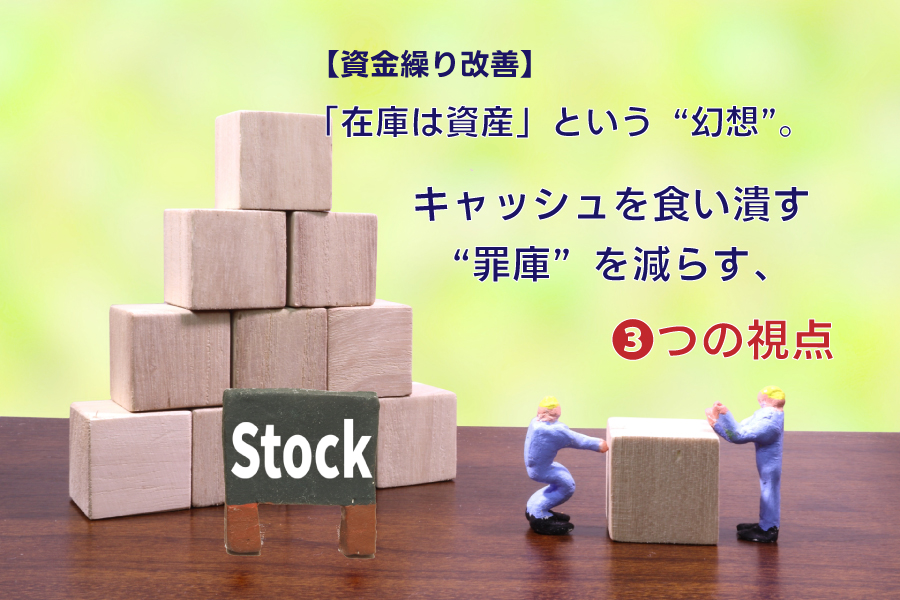
決算書の貸借対照表を開くと、「資産」の部に、大きな金額で計上されている「棚卸資産(在庫)」。その数字を見て、「これだけ資産があるのだから、うちの会社は安泰だ」と、安心のため息をついてはいないでしょうか。
しかし、経営の神様、ピーター・ドラッカーは、こう言いました。「在庫は、費用である」と。
会計上は「資産」であっても、経営、特にキャッシュフローの観点から見れば、売れない在庫は、会社の現金を静かに、しかし確実に食い潰していく、“罪庫(ざいこ)”とも呼べる、恐ろしい存在なのです。この記事では、その危険性と、“罪庫”を利益の源泉である「適正在庫」に変えるための、3つの視点を解説します。
会計上の「資産」と、経営上の「コスト」― 在庫が持つ、二つの顔
まず、なぜ在庫が「コスト」なのかを、正しく理解しましょう。あなたの会社が、100万円分の商品を仕入れた(あるいは、製造した)瞬間、会社の口座から、100万円の現金が、確実に出ていきます。
その在庫が、すぐに売れれば問題ありません。しかし、もし、それが倉庫で眠り続けるとしたら…。その間にも、あなたの会社には、様々なコストが発生し続けます。
- 保管コスト:倉庫の家賃、電気代、保険料
- 管理コスト:在庫を管理するための、人件費
- 陳腐化コスト:商品が古くなったり、流行遅れになったりして、価値が下がるリスク
- 機会損失コスト:在庫に化けた100万円を、もし、別のことに投資していたら、得られたかもしれない利益
このように、売れない在庫とは、持っているだけで、じわじわと会社の体力を奪っていく、高コストな存在なのです。
なぜ、「罪庫(ざいこ)」は生まれてしまうのか?
では、なぜ、こうした「罪庫」は生まれてしまうのでしょうか。その根本原因は、多くの場合、2つに集約されます。
原因①:需要の読み間違い
これは、「良いものを作れば売れるはずだ」という、作り手側の希望的観測が、市場のリアルな需要を上回ってしまった場合に発生します。顧客が「何を、どれだけ欲しているか」という、マーケティング(=届け方の糸)の視点が欠けているのです。
原因②:業務プロセスの滞り
営業、開発、製造といった、各部門間の連携が取れていない、「部分最適」の状態です。例えば、営業部門が、製造部門の生産能力を考えずに、大きな受注を取ってきてしまい、結果として、大量の仕掛品(作りかけの在庫)を抱えてしまう、といったケースです。
“罪庫”を、未来の利益に繋がる「適正在庫」に変える3つの視点
罪庫を減らし、キャッシュフローを改善するためには、以下の3つの視点から、自社の在庫管理を見直しましょう。
視点①:「見える化」― すべての在庫に、“住所”と“年齢”を与える
まず、自社に「何が、どこに、どれだけ、いつから」あるのかを、正確に把握することから始めます。手書きの在庫表や、担当者の記憶に頼るのではなく、簡単な在庫管理システム(ITツール)を導入し、全ての在庫をデータで「見える化」しましょう。こうしたツールの導入には「IT導入補助金」も活用できます。
視点②:「需要予測」― “勘”ではなく、“データ”で、未来を読む
次に、過去の販売実績や、市場のトレンドといった「客観的なデータ」に基づいて、未来の需要を予測する仕組みを、社内に作りましょう。「今年は、これくらい売れるだろう」という、経営者の“勘”だけに頼った生産計画が、最も多くの「罪庫」を生み出します。
視点③:「業務連携」― “部分最適”から、“全体最適”へ
営業部門は、販売予測を、製造部門と共有する。製造部門は、生産計画を、営業部門と共有する。このように、部門間の壁を取り払い、常に情報を連携させることで、会社全体として、最適な生産・在庫量を目指す「全体最適」の視点を持つことが重要です。
まとめ
貸借対照表の「資産」の部に、大きな金額で計上された「在庫」。それは、あなたの会社にとって、本当に「資産」だと言い切れるでしょうか。それとも、静かにキャッシュを蝕む「罪庫」の、サインではないでしょうか。
在庫は、あなたの会社の「戦略」と「オペレーション」の、健康状態を映し出す“鏡”です。
その鏡を、見える化し、データに基づいて、部門間で連携して磨き上げていく。その地道な取り組みこそが、会社の資金繰りを劇的に改善し、盤石な経営基盤を築き上げるための、王道なのです。


まずは「無料個別戦略診断」で、
現状と可能性を客観的に見つめ直すことから始めてみましょう 。