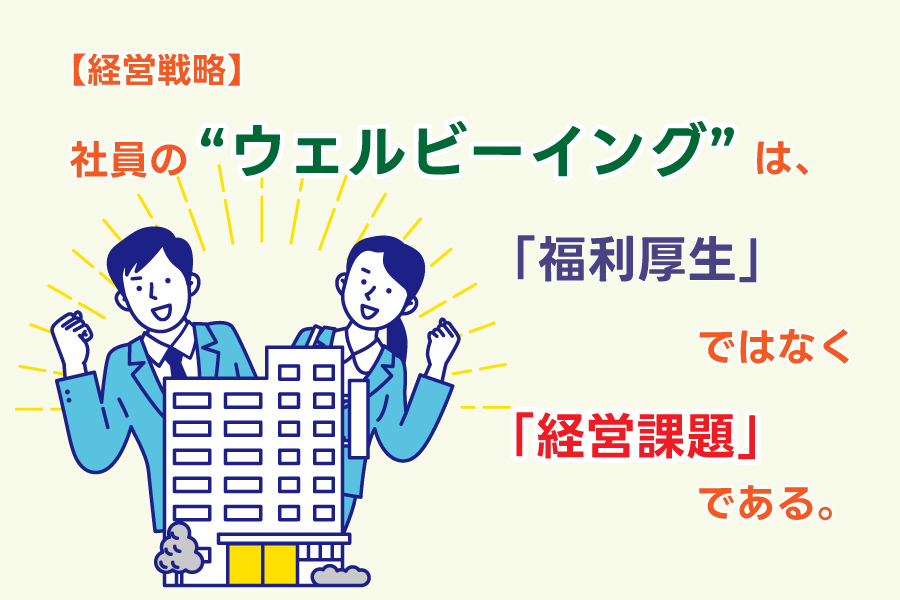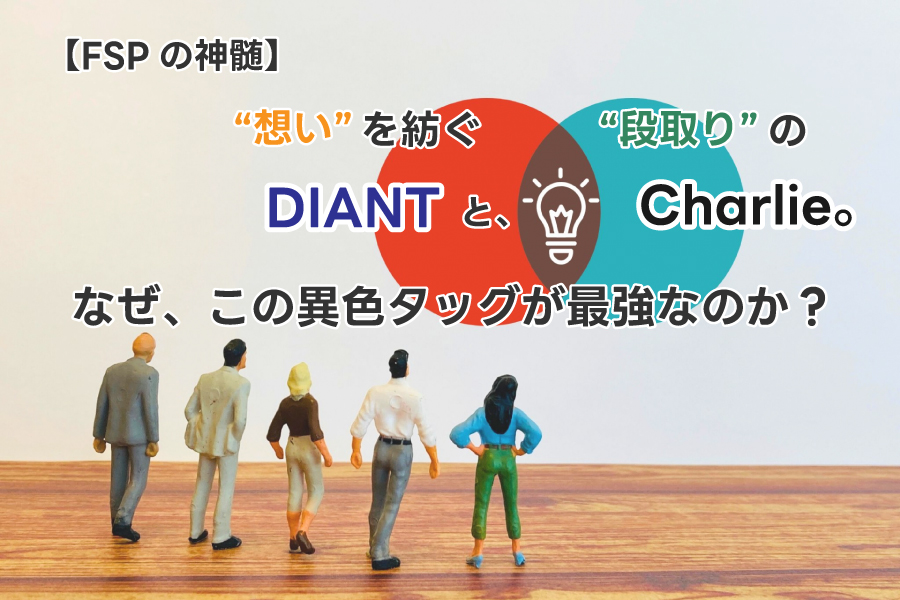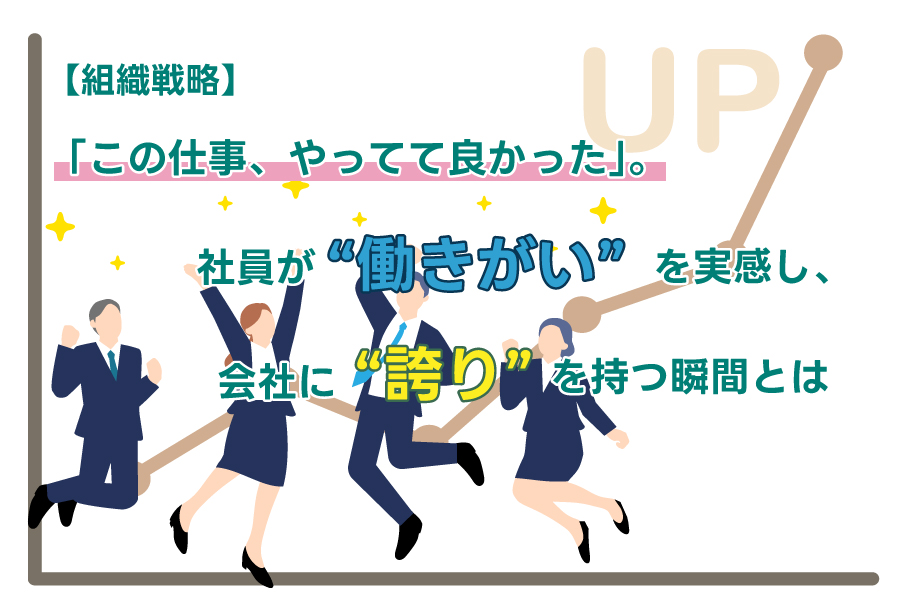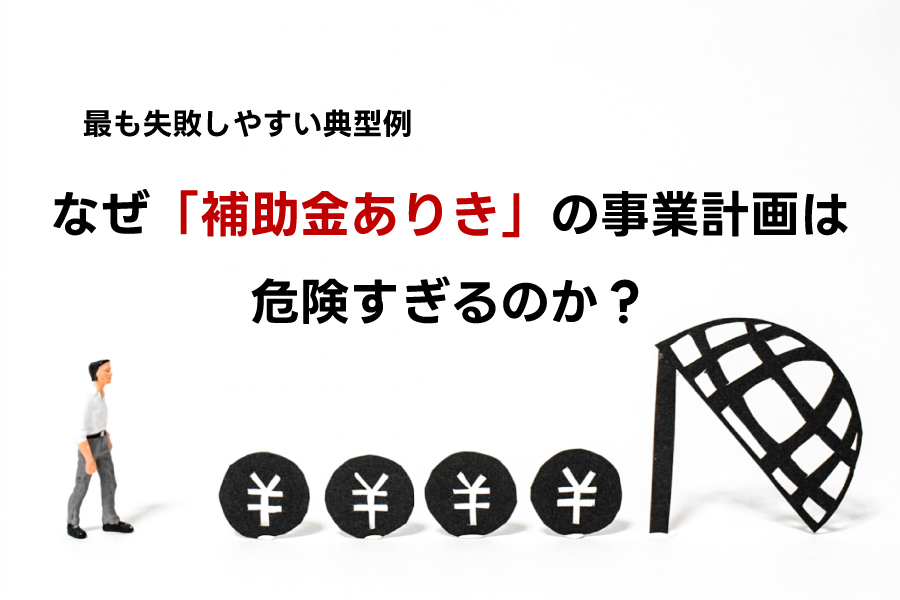
「来年度、XX補助金という大型の公募があるらしい。この補助金が使えそうな、新しい事業を計画しよう!」
一見、賢い資金調達のように聞こえるかもしれません。しかし、私たちFLAG-SHIFT-PROJECT(FSP)が、これまで見てきた数多くの失敗事例の中で、最も危険だと断言できるのが、この**「補助金ありき」**で始まる事業計画です。
なぜ、国が支援してくれるはずの補助金が、事業を失敗に導く最大の要因となってしまうのでしょうか。それは、「補助金ありき」の計画が、ビジネスの成功原則を根本から捻じ曲げてしまうからです。この記事では、その危険なメカニズムを3つの理由から解き明かします。
理由1:ビジネスの「目的」と「手段」が入れ替わるから
健全な事業計画は、必ず**「目的」**から始まります。
- 目的(WHY): 顧客のどんな課題を解決したいのか?市場にどんな新しい価値を提供したいのか?
- 手段(HOW): その目的を達成するために、どんな設備や人材、資金(補助金など)が必要か?
これがビジネスの鉄則です。しかし、「補助金ありき」の計画では、この順番が完全に逆転してしまいます。
- 手段(HOW): この補助金で何が買えるか?(例:最新のITツール、高性能な製造機械)
- 目的(WHY): そのツールや機械を使って、後から取ってつけたような事業目的を考える。
「補助金でウェブサイトが作れるから、新しいサイトを作ろう」と考えるのが「補助金ありき」の危険な思考です。本来は、「新規顧客に我々の価値を届けるために、ウェブサイトが必要だ。その費用の一部を補助金で賄えないか」と考えるのが正しい順番です。
手段が目的化した計画は、魂のない事業を生み出します。顧客の課題解決ではなく、**「補助金をもらうこと」**がゴールになってしまっているため、市場から見向きもされない独りよがりなサービスや製品が生まれるのです。
理由2:外部環境の変化に耐えられない「自走できない事業」が生まれるから
「補助金ありき」の計画は、いわば補助金という「温室」の中で育つ、ひ弱な植物のようなものです。計画のすべてが、補助金の公募要領や審査基準を満たすことに最適化されています。
- 審査員にウケが良いように、流行りのDXやSDGsといった言葉を無理やり事業計画に盛り込む。
- 本来は不要かもしれないが、補助対象経費になるからという理由で、過剰な設備を導入する。
こうして生まれた事業は、補助金という栄養剤がなければ生きていけません。市場の厳しい風雨(競合の出現、顧客ニーズの変化)に晒された途端、立ち行かなくなります。
これが、補助金採択企業の倒産原因の最多である**「販売不振」**の正体です。そもそも「市場で売るため」ではなく「補助金に採択されるため」に設計された事業なのだから、売れないのは当然の結果なのです。
理由3:本当に解決すべき「経営課題」から目を背けることになるから
多くの場合、「補助金ありき」の思考は、企業が抱える本質的な経営課題から目を逸らすための、甘い麻薬として機能します。
- 本当の課題: 長年の下請け体質で、価格競争から抜け出せない。
- 「補助金ありき」の解決策: とにかく生産性を上げるため、補助金で新しい機械を導入しよう。(→価格競争がより激化するだけ)
- 本当の課題: 会社の魅力が伝わらず、優秀な人材の応募が全くない。
- 「補助金ありき」の解決策: 補助金で派手な採用サイトを作ろう。(→根本的な魅力がないため、誰も応募しない)
補助金申請という「作業」に没頭している間は、これらの痛みを伴う本質的な課題と向き合わなくて済みます。しかし、それは問題の先送りにすぎません。補助金というカンフル剤の効果が切れ、より深刻化した課題と向き合うことになったときには、もう手遅れになっているのです。
まとめ
「補助金ありき」の事業計画が危険なのは、それがビジネスの成功法則を無視しているからです。
1. 「目的と手段」を逆転させ、顧客不在の計画を生む。
2. 市場で生き残れない「自走できない事業」を創り出す。
3. 目を向けるべき「本質的な経営課題」を先送りさせる。
補助金は、あくまでも、あなたが掲げた**「旗(=戦略)」に向かって進むための「追い風(=燃料)」**であるべきです。風向きに合わせて目的地を決める船が遭難するように、「補助金ありき」で事業の舵を取ることは、極めて危険な航海なのです。


まずは「無料個別戦略診断」で、
現状と可能性を客観的に見つめ直すことから始めてみましょう 。