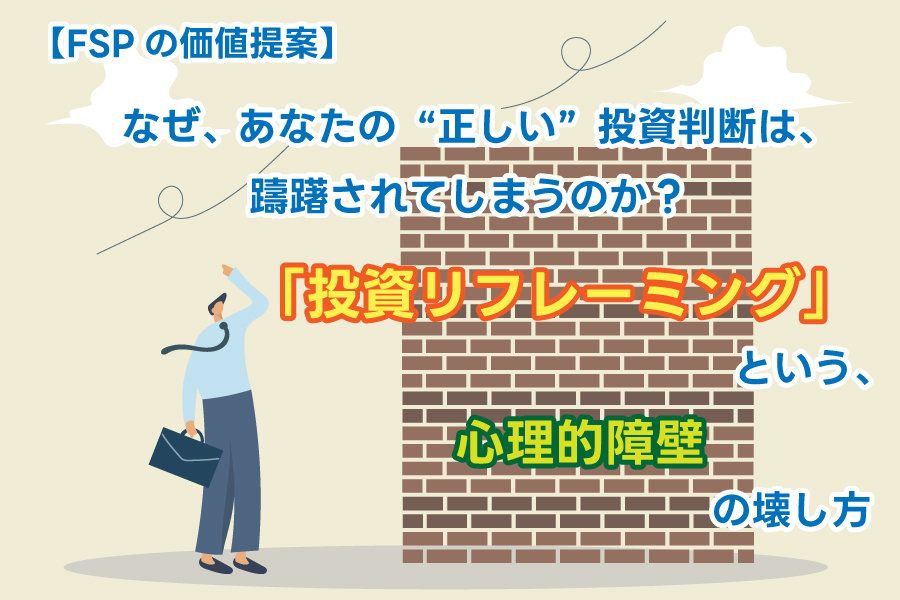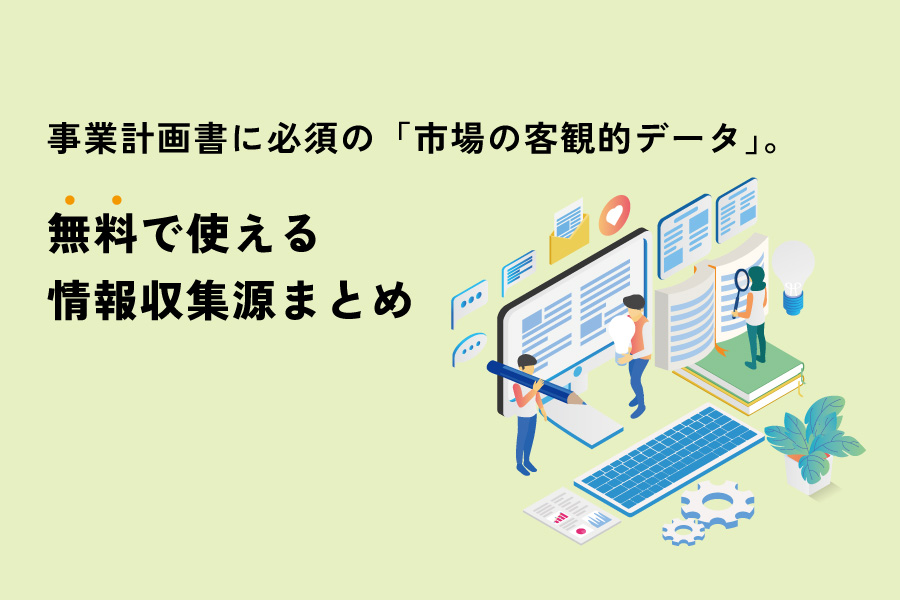
事業計画書の作成で、多くの経営者様が頭を悩ませる項目。
それが「市場規模・市場動向」の欄です。
「なんとなく、市場は伸びている気がする…」という感覚や願望だけでは、審査官や金融機関担当者を納得させることはできません。
補助金審査でマイナス評価を受ける事業計画書のワースト4は、まさにこの「根拠なき“願望”だけの計画書」です。
あなたの事業計画を、「願望」から「実現可能性の高い計画」へと昇華させる“客観的データ”。
この記事では、無料で使える信頼性の高い情報源と、その情報を効果的に収集・活用するためのコツを解説します。
なぜ「客観的データ」が、事業計画書の“心臓部”なのか?
- 事業の成功確率を高めるため:データに基づいた判断は、経営者の「思い込み」や「勘」によるリスクを低減させます。
- 計画の説得力を担保するため:「この経営者は、きちんと市場を分析した上で、この計画を立てているな」という信頼感に繋がり、公的な資金を投じるに足る、という判断の拠り所になります。
情報収集のコツ ―「仮説」を立ててから、データを集める
情報収集で最もやってはいけないのが、いきなり統計サイトを開き、闇雲に情報を探し始めることです。これでは、情報の海で溺れてしまいます。
情報収集の最大のコツは、「まず、自社の事業戦略に関する『仮説』を立てる」ことです。
【仮説の例】 「共働き世帯の増加に伴い、都市部では『時短』をテーマにした高品質な冷凍総菜の需要が高まっているはずだ」
この仮説があれば、集めるべきデータはおのずと決まってきます。
「共働き世帯数の推移」「冷凍食品の市場規模」「惣菜にかける一世帯あたりの金額」など、仮説を証明(あるいは反証)するためのデータを、狙い撃ちで探しにいけるのです。この手順を踏むことで、情報収集は、格段に効率的かつ戦略的になります。
【無料】FSPも活用する、信頼できる情報収集源まとめ
①市場の「大きな流れ」を掴む(マクロ情報)
- e-Stat(政府統計の総合窓口) 日本の人口、世帯数、各産業の統計など、国が実施するほぼ全ての統計データがここに集約されています。信頼性は抜群です。
- 各種白書(経済産業省、中小企業庁など) 「中小企業白書」や「ものづくり白書」など、各省庁が毎年発表するレポートです。業界全体の動向や、国がどんな課題を認識しているかを知る上で、非常に役立ちます。
②「競合」や「顧客」を具体的に知る(ミクロ情報)
- J-Net21(中小企業基盤整備機構) 中小企業向けの、非常に実践的な情報サイトです。様々な業種の「市場調査データ」や、ビジネスモデルのヒントとなる「成功事例」が豊富に掲載されています。
- 各業界団体のウェブサイト 飲食業、理美容業、建設業など、自社が所属する業界団体が、独自の統計データを公開していることがあります。非常に専門的で、価値の高い情報源です。
③ 地域の「生きた情報」を得る
国の大きなデータだけでなく、自社が事業を行う地域の「生きた情報」も重要です。
- 地域の金融機関(地方銀行・信用金庫)
- 地域の商工会議所・商工会 これらの機関は、地域独自の経済動向や、競合の動きなどを肌感覚で掴んでいます。数値データと合わせて、こうした定性的な情報を盛り込むことで、計画の解像度はさらに高まります。
まとめ
客観的データは、事業計画書の空欄を埋めるための「飾り」ではありません。
それは、あなたの事業戦略の確からしさを証明し、未来への羅針盤の精度を高めるための、不可欠なツールです。
そして、ただデータを貼り付けるだけでは不十分です。
「このデータから、このような市場機会が見込まれる。だから、我々はこのように挑戦する」という、データと自社戦略との「繋がり」を、あなた自身の言葉で語ること。
それこそが、審査官の心を動かし、採択を勝ち取る事業計画書の、最後の決め手となるのです。


まずは「無料個別戦略診断」で、
現状と可能性を客観的に見つめ直すことから始めてみましょう 。