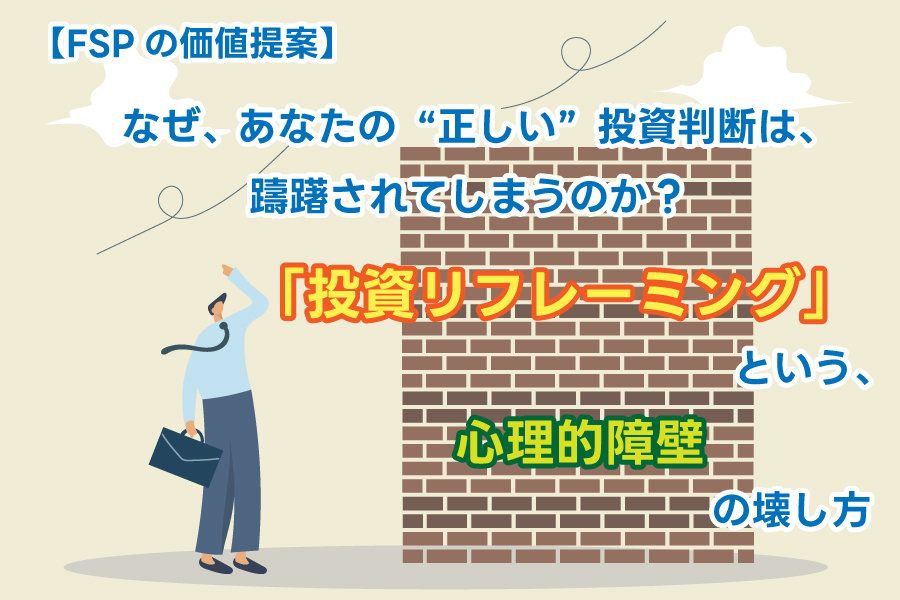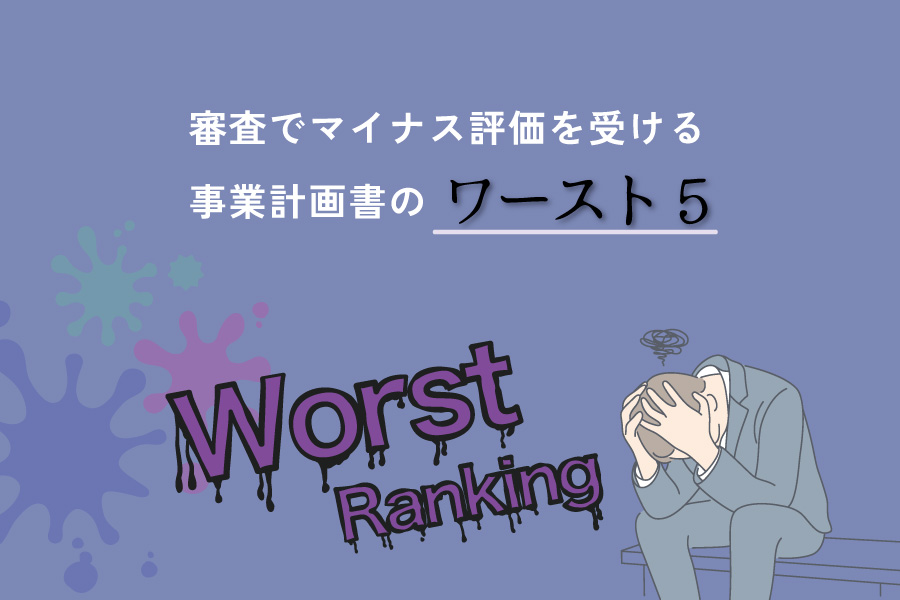
補助金の審査は、加点方式であると同時に、致命的な欠陥をふるい落とす「減点方式」の側面も持っています。
どんなに素晴らしい事業アイデアも、計画書の書き方一つで、その価値が全く伝わらず、マイナス評価を受けてしまうことがあるのです。
「熱意を持って書いたのに、なぜか採択されない…」 その原因は、あなたも気づかないうちに、不採択に直結する「ワーストな計画書」の罠にハマっているからかもしれません。
この記事では、審査官が思わず首を傾げてしまう事業計画書のワースト5をランキング形式で発表し、そのマイナス評価をどうすれば克服できるのか、具体的な対策を解説します。
ワースト5:神は細部に宿る ― 不備や誤字脱字だらけの計画書
【これはNG】 会社名や代表者名に誤字がある。計算が合っていない。提出書類が一部抜けている…。こうしたケアレスミスは、「この経営者は、事業運営においても脇が甘いのではないか?」という、致命的な不信感を審査官に与えます。
【マイナスをなくすには】 これは、「段取り術」で100%防げるミスです。申請ボタンを押す前に、必ず自分以外の第三者に、公募要領と照らし合わせながら全項目をダブルチェックしてもらう体制を作りましょう。プロの仕事は、細部にこそ宿ります。
ワースト4:ただの「ほしい物リスト」― 根拠なき“願望”だけの計画書
【これはNG】 「最新の機械を導入すれば、売上は3倍になります」「新しいホームページを作れば、全国から注文が殺到するはずです」。なぜそう言えるのか?という客観的なデータや市場分析が一切なく、ただ経営者の「願望」だけが書かれている計画書です。
【マイナスをなくすには】 全ての目標に、具体的な「根拠」を示しましょう。FSPのフレームワークでいう「届け方の糸(DI)」の考え方です。どの市場の、どんなニーズを持つ顧客に、どうアプローチするから、この売上目標が達成できるのか。そのロジックを明確にすることで、「願望」は「実現可能な計画」へと変わります。
ワースト3:言動が不一致 ―「物語」に矛盾だらけの計画書
【これはNG】 「我々の強みは、職人による丁寧な手仕事です」と理念を語りながら、事業計画の中身は「コスト削減のための、全自動の量産機導入」だったりするケース。これでは、物語に一貫性がなく、審査官は「この会社の本当の価値は何なのだろう?」と混乱してしまいます。
【マイナスをなくすには】 企業の「想い」と「行動」を一貫させることが重要です。「5つの糸」のフレームワークを用いて、自社の理念(想いの糸)から、具体的な投資計画(行動の糸・届け方の糸)までを、一本の線で結びつけることで、計画全体の説得力が飛躍的に高まります。
ワースト2:誰の顔も見えない ―「想い」や「熱意」が不在の計画書
【これはNG】 まるで他人事のように、淡々と事実だけが書かれている計画書です。経営者である「あなた」の、この事業にかける熱い想いや、製品・サービスを待っている「顧客」の顔が全く見えてきません。これでは、審査官の心は動きません。
【マイナスをなくすには】 事業計画書は、あなた自身の「物語」を語る場です。なぜこの事業を始めたのか、どんな困難を乗り越えてきたのか、そしてこの補助金を活用してどんな未来を創りたいのか。あなたの「想いの糸(MI)」を、自分の言葉で正直に語ることで、計画書に血が通い始めます。
ワースト1:結局、どうやって稼ぐの?―「販売戦略」が皆無の計画書
【これはNG】 導入したい機械の性能や機能については何ページも詳細に書かれているのに、「で、それをどうやって売るの?」という最も重要な問いへの答えが、一行も書かれていない計画書。これが、補助金採択後に「販売不振」で倒産する、最も典型的なパターンです。
【マイナスをなくすには】 事業計画書の半分は、「販売戦略」にページを割くくらいの気持ちで作成しましょう。「誰に」「何を」「いくらで」「どこで」「どのようにして」販売するのか。その具体的なアクションプランを示すことで、審査官は「この計画なら、投資した資金をしっかりと回収し、成長してくれるだろう」と、安心して投資判断を下せるのです。
まとめ
不採択となる事業計画書のワースト5は、突き詰めれば、
「戦略なき、思いつきの計画」という一つの言葉に集約されます。
これらのマイナス点を一つ一つ潰していく作業は、単なる書類作成のテクニックではありません。
それは、自社の経営そのものを見つめ直し、未来への「価値の旗」を掲げ直す、極めて重要な戦略策定プロセスなのです。


まずは「無料個別戦略診断」で、
現状と可能性を客観的に見つめ直すことから始めてみましょう 。