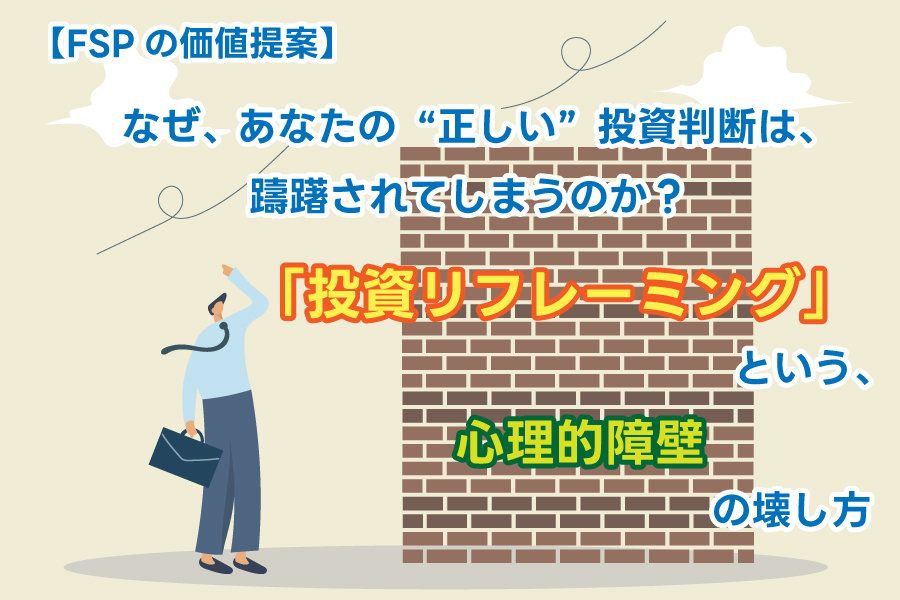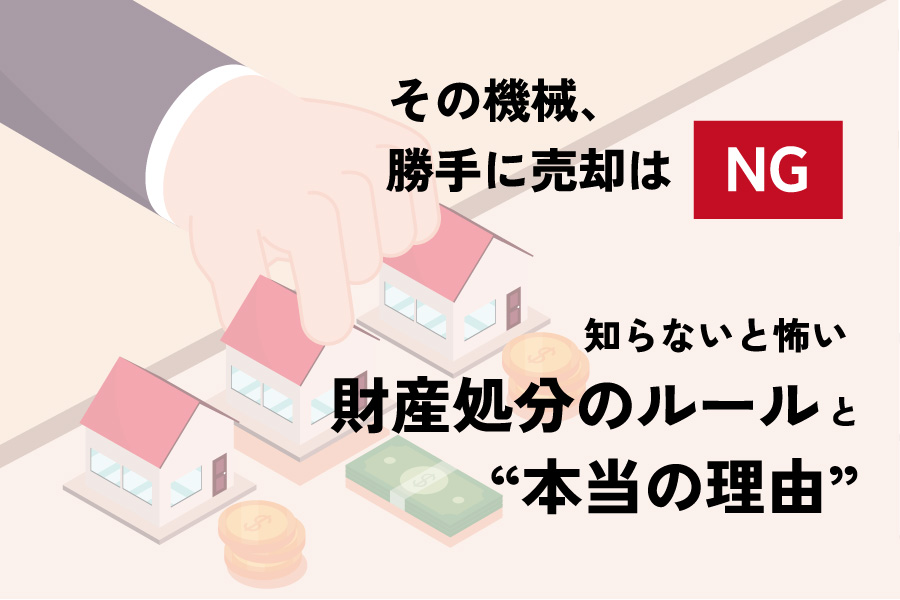
補助金を活用して導入した、念願の最新設備。数年が経ち、さらに高性能な新型機が登場した。
「この古い機械を売却して、新しい機械の購入資金の足しにしよう」
経営者として、ごく自然な判断に思えるかもしれません。
“ちょっと待った!”その自己判断が、補助金の「返還命令」という、最悪の事態を引き起こす可能性があるのです。
補助金で購入した資産には、「財産処分」に関する、極めて厳しいルールが定められています。
この記事では、なぜ資産を自由に処分できないのか、その本質的な理由と、万が一の際の正しい手続きについて解説します。
「財産処分」とは?― 補助金で購入した資産にかけられた“縛り”
まず、言葉の定義を整理しましょう。
補助金における「財産処分」とは、補助金で購入した資産(機械、設備、ソフトウェアなど)を、国の承認を得ずに、
- 売却する(転売・譲渡)
- 廃棄する(スクラップ)
- 他社に貸し出す(貸付)
- 借金の担保に入れる(担保権の設定)
といった行為を指します。これらの資産には、法律で「財産処分制限期間」(例えば、機械装置なら通常5年間など)が定められており、この期間内に無断で処分することは、固く禁じられています。
【本質】なぜ、資産の処分に、いちいち国の承認が必要なのか?
「自分のお金も出して買った、自社の資産なのに、なぜ自由に売ったり捨てたりできないんだ?」と感じる方もいらっしゃるでしょう。その理由は、補助金の「原資」と「目的」を考えると、至極当然のこととして理解できます。
理由①:補助金は「国民の税金」だから
補助金の原資は、国が集めた「国民の税金」です。
つまり、あなたの会社が受け取った補助金は、政府からのプレゼントではなく、国民全体からの「未来への投資」なのです。
国は、その資金の管理者として、税金が本来の目的通り、正しく使われているかを監督する責任があります。
そのため、投資対象である資産が、勝手に転売されて利益に変えられたり、計画と違う目的で使われたりしないよう、厳しく管理する必要があるのです。
理由②:「事業の継続」と「政策目標の達成」が大前提だから
あなたの会社が採択されたのは、「この投資によって、生産性を向上させ、雇用を増やし、賃金を上げ、日本経済に貢献します」という、素晴らしい事業計画(=国民への約束)を提示したからです。
補助金で購入した資産は、その「約束」を果たすための、最も重要な“武器”のはずです。
もし、その武器を約束の期間の途中で、勝手に手放してしまえば、事業計画そのものが成り立たなくなり、国民との約束を破ることになります。
国の承認が必要なのは、「たとえ、その資産を処分したとしても、当初計画した事業目的や政策目標は、きちんと達成されるのですね?」ということを、国が確認するためなのです。
もし、どうしても処分が必要になったら?(正しい手続きの踏み方)
とはいえ、事業を続けていれば、設備の故障や、事業内容の変更など、やむを得ない事情で資産を処分せざるを得ないケースも出てきます。その際は、絶対に自己判断せず、以下の正しい手続きを踏んでください。
- まずは事務局に相談:補助金の事務局に連絡し、事情を説明して、必要な手続きを確認します。
- 財産処分承認申請書を提出:指定された書式で、処分の理由や内容を記載した申請書を提出します。
- 承認後、処分を実行:事務局から正式な承認を得て、初めて資産の処分が可能になります。
- 場合によっては、補助金の一部を返納:資産の売却によって収益が出た場合などは、その収益額を上限として、補助金の一部を国に返納するよう指示されることがあります。
まとめ
補助金で購入した資産の「財産処分」に承認が必要なのは、決して理不尽なルールではありません。
それは、「国民の税金で事業を成長させる」という、公的なプロジェクトに参加する者としての、当然の責任なのです。
補助金で購入した資産は、単なる「自社のモノ」ではなく、「国民との約束を果たすための、大切な預かり物」である。この意識を持つことが、思わぬルール違反を防ぎ、あなたの会社をリスクから守る、最大の防衛策となります。


まずは「無料個別戦略診断」で、
現状と可能性を客観的に見つめ直すことから始めてみましょう 。